お知らせ
林家正雀師匠 来たる!
2015年12月20日
2016年お正月の行事は、元日恒例の「修正会」に続き、11日(成人の日)に「新春法会」が開催されます。第2部の落語会には林家正雀師匠がお越しくださいます。お楽しみに!皆様ぜひお出かけください。
※詳細はこちら→ 2016新春法会

1月・2月の行事案内
2015年12月20日
1月
◇修正会
1月 1日(金)元日 10時
〈日 程〉開扉・静座・勤行・献杯・挨拶
◇新春法会
1月11日(月)成人の日
〈日 程〉13時30分 勤行・挨拶
14時 落語(林家正雀・豊田家金平ほか)
15時30分 福引・懇親会
◇真宗大谷派東京教区 報恩講(東本願寺真宗会館)
1月26日(火)10時30分 帰敬式(法名授与式)
1月27日(水)11時30分 逮夜法要 法話 池田勇諦 先生(同朋大学名誉教授)
16時30分 報恩講の夕べ 「ライブ・イン・浄土の真宗」えにしを生きる
1月28日(木) 8時 晨朝法要 法話 朝倉俊隆 先生(東京・報土寺)
10時30分 日中法要 法話 池田勇諦 先生(同朋大学名誉教授)
※詳細はこちら→東京教区報恩講http://www.ji-n.net/gyoji/houonkou.html
2月
◇お寺でカラダもリフレッシュ!「ピラティス教室」(申込制)
2月 4日(木)13時30分
〈指 導〉竹井景子さん(ピラティス&ジャイロキネシス トレーナー /ダンス インストラクター) 〈参加費〉500円
※ヨガと同じストレッチ効果とともに、体幹の筋肉を鍛え、脊柱や骨盤も整えていく「ピラティス」。普通に生活しているだけでは失われていく筋力を回復させてくれます。トレーナーの竹井景子さんは専行寺ご門徒のお嬢さんです。一人ひとりにあったトレーニングで指導してくださいます。
※お申込みは専行寺へどうぞ。
◇「仏教入門講座」
2月 4日(木)14時30分~16時30分
〈法 話〉「正信偈のこころ」海 法龍 先生(長願寺住職 / 首都圏広報誌『サンガ』編集委員)
〈参加費〉500円
※これから仏教を聞いていきたいという方にもわかりやすい入門講座。偶数月開催。
◇「真宗大谷派東京4組同朋会」
2月19日(金)13時30分~16時30分
〈会 場〉諦聴寺(渋谷区代々木3-26-1)
〈テーマ〉「私が仏に求められていること」―真宗が利益―
※申込制(詳細は専行寺までどうぞ)
「五箇山・井波・金沢をめぐる旅」ご報告
2015年12月05日
11月24日から26日にかけて秋の参拝旅行に出かけてまいりました。
往復とも北陸新幹線を利用した今回の旅、初日は富山県南砺の五箇山、妙好人「赤尾の道宗」ゆかりの行徳寺と世界遺産・相倉合掌造り集落へ。2日目は井波彫刻の粋を集める真宗大谷派井波別院・瑞泉寺と城端別院・善徳寺、そして版画家・棟方志功ゆかりの福光へ。志功が戦時中疎開していた光徳寺と福光美術館では大胆かつ荘厳な作品の数々を拝観することができました。3日目は東尋坊から蓮如上人(本願寺八代)ゆかりの吉崎御坊と金沢・兼六園へ。
富山県南砺地方では綽如上人(本願寺五代)・蓮如上人以来の伝統として「講」と呼ばれる寄り合いの場で念仏の教えが相続されてきました。今でもその教えのもとに互いに支え合いながら暮らす「結(ゆい)」「合力(こうりゃく)」と呼ばれる精神が人々を繋いでいます。棟方志功の心に響き、柳宗悦の民藝美論にも新たな方向性を与えたといわれるこの地の精神風土。「土徳」と呼ばれるものにふれた気がした旅でした。










「報恩講」が勤められました。
2015年11月17日
11月3日(火)文化の日
宗祖親鸞聖人の報恩講(754回忌)が勤められ、大勢の皆様にお参りいただきました。法要を縁に帰敬式(法名授与式)も執行されました。
ご法話は、専行寺の仏教入門講座にもご出講いただいている海法龍先生(真宗大谷派 首都圏教化本部本部員・長願寺住職)。帰敬式にちなんで、仏弟子のこころ、法名等について懇切にお話しくださいました。
〈法話聞書〉
親鸞聖人はお寺を道場「ナラフイエ」と教えてくださいました。仏法(道理)を「習う家」です。仏法にふれて自分の生き方が定まったと仰いました。仏法にふれるにはそのこころにふれた人に出遇うことです。知識や解釈や教養でなく、自分の生き方として道理にうなずいた方々に出遇っていかなければなりません。そういう方々を「諸仏」といいます。教えに出遇った方々です。しかしご自分で「自分は諸仏だ」とは仰いません。親鸞聖人も自分はいつも弟子習う者という立ち位置だと仰っておられました。ですから真宗門徒は僧も俗も等しくお釈迦様の「釋」の一字を苗字として「釋氏」を名のる。それが法名です。
親鸞聖人の主著『教行信証』の正式名称は『顕浄土真実教行証文類』です。「浄土は真実であるということを顕かにする」ということですが、「真実ということを浄土という言葉を通して顕かにする」とも読めるわけです。私たちが真実にふれるための教えであり歴史である、と。仏教は私たちに「真実」「ほんとう」ということを伝えたい。なぜかというと、私たちが意識の底で「ほんとう」を求めているからです。気づかないかもしれないけれど、いい悪い、損得ということを超えて、私たちの内底に実は「ほんとう」ということを求めている心が流れているのです。仏教はそれを「菩提心」と呼びます。一般的な言い方では「宗教心」です。
一人ひとりの存在は尊い。しかしそれに背く人間がある。そのことを深く傷み悲しみ、自分自身の姿に目覚めてほしい、という願いが生まれ、それが南無阿弥陀仏の教えとなって私たちのところに届いています。「如」とは「あるがまま」。「いのちは皆尊い」ということをあらわします。それが私たちのところに来るから「如来」といいます。私たちが背いているから「如来大悲」。「ほんとう」ということにふれてほしいという呼びかけです。「他者とどう向き合っているのか?」「私のこころはどこに立っているのか?」私のこころのあり方をいつも問い返して、人々と同じ命を生きているんだというところに立ち返るような世界を私たちに開いてくださいます。そのことを私たちが生活の中でいただいていくことが願われ求められているのではないでしょうか。
※次回の定例法要は、2016年1月1日(金)に勤められる「修正会」です。ぜひお参りください。
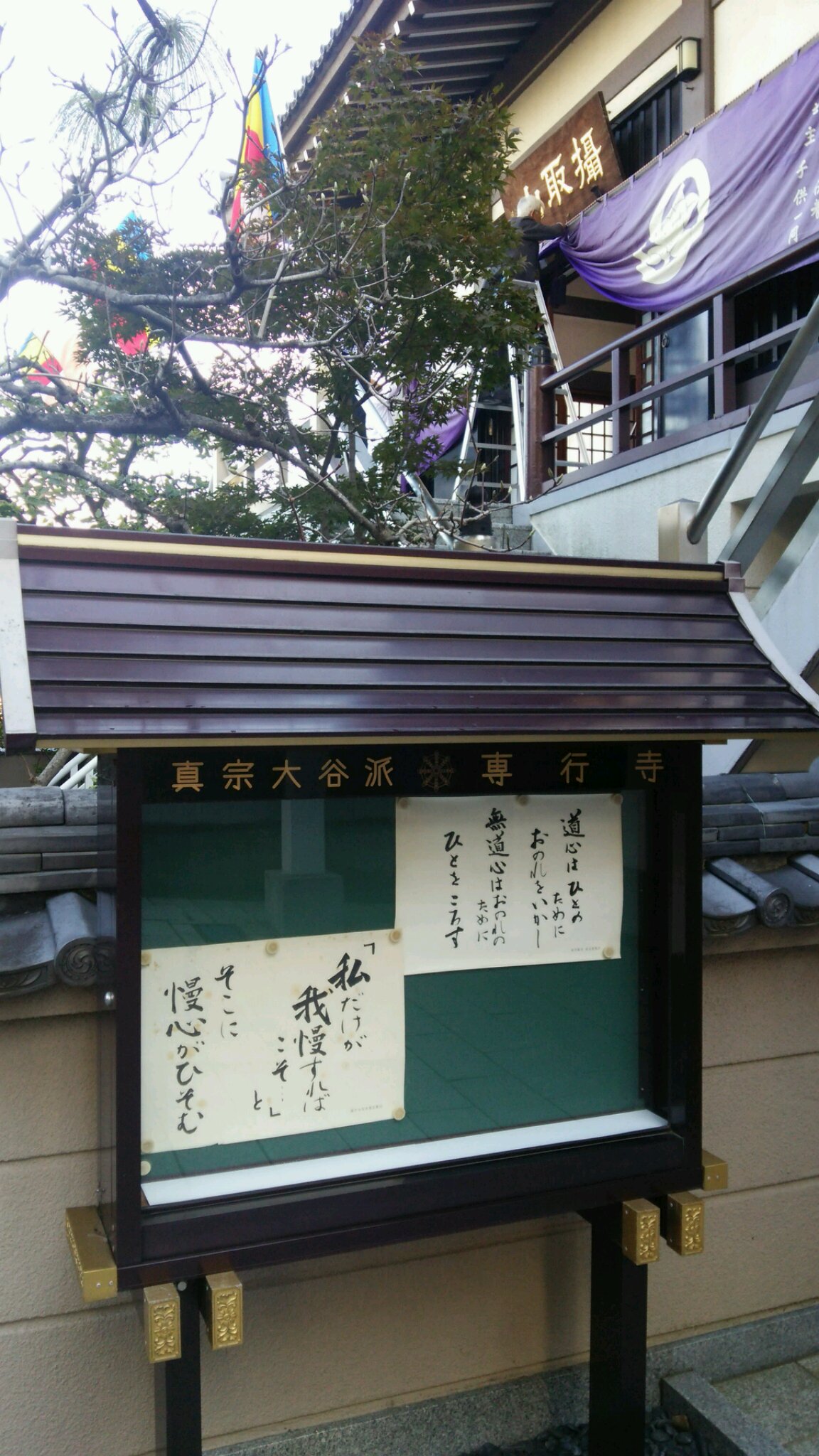






11月・12月の行事案内
2015年10月29日
11月
◇報恩講(宗祖親鸞聖人754回忌)
11月3日(火)11時~14時(終了後、懇親会)
〈日程〉勤行・お斎(精進料理)・法話
〈法話〉海 法龍 先生(長願寺住職 / 真宗大谷派首都圏教化推進本部 本部員)
※10時15分より帰敬式(法名授与式)が執行され、新しく仏弟子が誕生します。ぜひ皆様ご参列ください。
◇生を見つめるための「入棺体験会」(申込制)
11月4日(水)19時~20時45分
〈日程〉➀挨拶 ➁環境にやさしいお棺「エコフィン」の説明 ➂入棺体験 ➃話し合い(軽食あり) ➄プチ法話
※私たちは「生死一如」のいのちを生きています。ふだん眼を背けている「死」というものにきちんと向き合ってみると、おのずと自分の「生」を見つめる眼が与えられます。いま終活ブームといわれていますが、ほんとうの意味での「終活」は、その眼をいただくところから始まるのではないでしょうか。毎回、初めてお寺に足を運ぶお若い方々も参加されています。どうぞお気軽にお出かけください。
※「生き方」と「逝き方」を楽しく学び合うコミュニティ“これから楽交(がっこう)”と専行寺とのコラボ企画です。
※お申込みは専行寺へどうぞ。
◇参拝旅行会「五箇山・井波・金沢をめぐる旅」
11月24日(火)~26日(木)
〈参加費〉89.000円(各寺参拝志納金を含む)
コース (都合により変更になる場合もあります)
11/24(火) 東京駅(7時30分集合 ⇒〈北陸新幹線〉⇒新高岡駅(専用バス)⇒〈東海北陸自動車道〉⇒西赤尾・ささら館(昼食) ⇒ 赤尾・行徳寺(妙好人 道宗の寺)・岩瀬家⇒五箇山合掌造り 相倉集落 ⇒ 庄川温泉「ゆめつづり」
11/25(水) 宿 ⇒ 井波別院・瑞泉寺(井波彫刻の粋を堪能できる真宗大谷派の別院)・門前町散策 ⇒城端別院・善徳寺(蓮如ゆかりの越中念仏道場。本尊阿弥陀如来は行基作) ⇒道の駅「福光」(昼食)⇒福光・光徳寺(版画家・棟方志功が疎開していた寺。多作品を所蔵)⇒福光美術館 ⇒〈北陸自動車道〉⇒ 山代温泉「菖蒲亭」
11/26(木) 宿 ⇒東尋坊⇒吉崎別院(蓮如ゆかりの吉崎御坊跡)⇒〈北陸自動車道〉⇒金沢・見兼御亭(昼食)兼六園ほか ⇒金沢駅 ⇒〈北陸新幹線〉⇒東京駅(19時頃帰着予定)
※詳細は専行寺までどうぞ。定員25名ですので、お早めにお申し込みください。
※参加お申込みいただいた方には集合などの詳細を出発2週間前に連絡致します。
◇「宗祖親鸞聖人御正忌報恩講」
11月21日(土)~28日(土)京都・東本願寺
12月
New!
◇お寺でカラダもリフレッシュ!「ピラティス教室」(申込制)
12月7日(月)13時
〈指 導〉竹井景子さん(ピラティス&ジャイロキネシス トレーナー /ダンス インストラクター) 〈参加費〉500円 ※ヨガと同じストレッチ効果とともに、体幹の筋肉を鍛え、脊柱や骨盤も整えていく「ピラティス」。普通に生活しているだけでは失われていく筋力を回復させてくれます。トレーナーの竹井景子さんは専行寺ご門徒のお嬢さんです。一人ひとりにあったトレーニングで指導してくださいます。
※お申込みは専行寺へどうぞ。
◇「仏教入門講座」
12月7日(月)14時30分~16時30分
〈法 話〉「正信偈のこころ」海 法龍 先生(長願寺住職 / 首都圏広報誌『サンガ』編集委員)
〈参加費〉500円
※これから仏教を聞いていきたいという方にもわかりやすい入門講座。偶数月開催。
◇「真宗大谷派東京4組同朋会」
12月12日(土)13時30分~17時30分
〈会 場〉安閑寺(文京区白山2-13-13)
〈講 師〉渡辺智香 先生(西福寺住職)
〈参加費〉1000円
※詳細は専行寺までお問合せください。
◇修正会に向けての「仏具お磨き奉仕」「年末煤払い奉仕」
12月25日(金)10時~12時(作業終了後、昼食)午後は「煤払い」
※作業しやすい服装でお出かけください。昼食は寺で用意します。
※ご奉仕の可能な時間だけのご参加でも結構です。ご協力をお願いします。
「仏具お磨き奉仕」「輪読会」が開催されました。
2015年10月29日
10月26日(月)
報恩講に向けての「仏具お磨き」と、午後からは「輪読会」が開催されました。
「仏具お磨き」
本堂に置かれている花瓶やローソクの燭台などの真鍮製仏具をすべて下ろし、ひとつ一つ丹念に磨いていただく奉仕作業です。真鍮ですので磨くと見事に輝きを取り戻します。今回は14名の方にご協力いただきました。おかげさまでピカピカの仏具で法要を迎えることができます。皆様ありがとうございました。
専行寺では年6回の定例法要の前に「仏具お磨き」をお願いしています。奉仕活動を通して、仏さまをより身近に感じていただければ幸いです。終了後は書院でのランチタイムです。
次回は12月25日(金)10時から。(午後は年末お煤払い)
※作業しやすい服装でお出かけください。昼食は寺で用意します。
※ご奉仕の可能な時間だけのご参加でも結構です。皆様のご協力をお願い致します。



「輪読会」
『同朋新聞』(真宗大谷派発行)や『サンガ』(東本願寺真宗会館 首都圏広報誌)などをご一緒に読み、感想を語り合っています。今回は以下の文章が話し合いの手がかりとなりました。どなたもお気軽にどうぞ。
『同朋新聞2015・11』 インタビュー結城幸司さん「大地に学ぶ―アイヌの精神文化に聞く―」より
インタビュアー「人間を中心にした、勝ち負けや損得、あるいは正義といったことではない世界。そこに人間からのまなざしではなく、人間を見つめている大いなるはたらきの世界(大地性)があるのを感じます。仏教にも浄土とか大信海とか、そこで人間がお育てをあずかるような大事な言葉や場があったのですけれども、それが身体性を失うとともにどんどんなくなってきて・・・」
結城氏「・・・身体性ということで言えば、やはり自分の身をとおした言葉で語るということは大事です。こころから発せられる言葉をぶつけないと。お坊さんのお話を聞くにしても、親鸞の言葉や、仏さまの言葉であっても、本当に感動するのは、親鸞の言葉をそのまましゃべる人ではなく、自分の言葉としてしゃべる人なんですよね。僕らアイヌ文化もそうなんです。文化を伝えるガイドはいくらでもできる。でも、そこの中に自分がアイヌ文化を愛しているのかとか、先人に敬意があるのかは絶対わかるんですね。人間は言葉に出遇い、言葉に導かれてゆくのです。逆に、自分の身体をとおさない言葉は人間をだめにしていくのかもしれないですね」


「仏教入門講座」と「ピラティス教室」が開催されました。
2015年10月05日
10月1日(木)
「仏教入門講座」が開催されました。ご法話は海法龍 先生。「正信偈のこころ」をテーマにお話しいただいています。今回は『正信偈』依経分の結び「弥陀仏本願念仏・邪見憍慢悪衆生・信楽受持甚以難・難中之難無過斯」というお言葉を中心にお話しいただきました。
〈法話聞書〉
「私たちは方向性が定まりません。本願の名号(南無阿弥陀仏)は、本当の意味での方向を定めてくる。それは、方向性を決めている私の立っているところ、立ち位置。それがどこなのかということがはっきりするということです。どこに立っての政治か?どこに立っての教育か?どこに立っての医療か?どこに立っての僧侶か?どこに立っての親か?それがはっきりすれば、それぞれの道が自ずと開かれてくるのです。“至心信楽”という真実の世界。本当というところに立たなければいけないのではないか。私たちが立っているところは実は本当でないところに立っているのではないか。本当という方向性を示してくださっているのです」
「“至心”とは真実。浄土の世界。彼岸の世界。西方極楽浄土。西方十万億土だと教えられます。十万億土という遠いところにあるという表現ですが、それは人間の迷いの心が深いということです。本当のことは私たちのところにあるのだけれども、私たち自身にそれを見る力、眼がない。つまり教えが難しいのではない。私たち自身に難しいものがある。“信楽受持甚以難” 信楽を受持することはなはだ難し、です。教えが難しいのではなくて、私の心が難しい。私の心が迷いだから、その迷いの心で見えない。親鸞聖人の見方というのは方向が逆転するわけです。私たちはいつも教えを対象化する。南無阿弥陀仏を向こうにおいて難しいと言っている。向こうから言えば、難しい原因は私たちにある。そのことに目を覚ましてほしいから教えの言葉が願いとして生まれてきているのです」
〈次回予定〉
日時 12月7日(月)14時30分から。
法話 「正信偈のこころ」海法龍 先生(長願寺住職/首都圏広報誌『サンガ』編集委員)
※これから仏教を聞いていきたいという方にもわかりやすい入門講座です。連続講座ですが途中からでもお気軽にどうぞ。

引き続き「ピラティス教室」が開催されました。
ピラティスはヨガと同じストレッチ効果とともに、体幹の筋肉を鍛え、脊柱や骨盤も整えていく運動です。今回は法話をお聞きした後にカラダもリフレッシュするひとときとなりました。皆さんリラックスして体をほぐされました。トレーナーの竹井景子さん(ピラティス&ジャイロキネシス トレーナー /ダンス インストラクター)は専行寺ご門徒のお嬢さんです。一人ひとりにあったトレーニングで指導してくださいます。
〈次回予定〉
日時 12月7日(月)13時から。
※定員10名。申込制。専行寺までお申込みください。

「秋彼岸法要」が勤められました。
2015年09月23日
9月20日(日)
秋の彼岸法要が勤められ、大勢の皆様がお参りくださいました。仏前で手を合わせてお念仏申すご縁をいただくということは、私たちを導いてくださる諸仏として亡き人と出会い直す、新しい関係性の始まりでありましょう。ご法話は松井憲一先生(京都・道光舎主宰・道専寺前住職)。新聞の投書や川柳などから、生活実感を大切にされたお話をいただきました。
〈法話聞書〉
「彼岸はちょうど太陽が真西に沈むということから、西を仰いで西方浄土を想う日。太陽というのは生命の象徴ですから、いのちの帰るべき方向です。『西』という文字は鳥の巣の形からできた象形文字ですから、私たちが本当に安心して帰れる場所、そういう方向を思い直す日です」
「私たちは日頃、物質的豊かさだけを求めて、かけがえのない時間を空しく過ごし、ついつい人間らしい自分の姿を見つめるということを忘れています。こういう法要を縁に帰るべき方向がはっきりと定まること。阿弥陀仏の本願によって荘厳された世界に真向かいになって、わが身をもう一度問い直すこと。これが彼岸会の内容といえます」
「一般的には、『人事を尽くして天命を待つ』ですね。一生懸命やってあとは天命を待つ。清沢満之先生は、そうではなくて「天命に安んじて人事を尽くす」と。他力に安んじて、本願に安んじて、念仏に安んじて、自力を尽くさせてもらう。自力がアカンというのではありません。「私がやったんだ!」という自力は問題だけど・・・。生かされている力・背景があるからこそ、私は私なりの力を尽くさせていただくことができる。そういうひっくり返しがあることを南無阿弥陀仏という言葉で教えてくださるわけです」
「こうして諸仏のお導きをいただいて念仏を申す、自力を尽くす世界を頂戴していくということが、こういう彼岸会に遇う大事な大事なご縁なのです」
※次回の定例法要は、11月3日(火)文化の日に勤められる報恩講です。帰敬式(法名授与式)も行われます。法話は海法龍先生(長願寺住職・真宗大谷派 首都圏教化推進本部 本部員)。 現在、専行寺の仏教入門講座の講師も務めていただいています。ぜひお参りください。




「仏具お磨き奉仕」「輪読会」が開催されました。
2015年09月15日
9月14日(月)
午前中に秋彼岸法要に向けての「仏具お磨き」、午後からは「輪読会」が開催されました。
「仏具お磨き」
本堂に置かれている花瓶やローソクの燭台などの真鍮製仏具をすべて下ろし、ひとつ一つ丹念に磨いていただく奉仕作業です。真鍮ですので磨くと見事に輝きを取り戻します。今回は11名の方にご協力いただきました。おかげさまでピカピカの仏具で法要を迎えることができます。皆様ありがとうございました。
専行寺では年6回の定例法要の前に「仏具お磨き」をお願いしています。奉仕活動を通して、仏さまをより身近に感じていただければ幸いです。終了後は書院でのランチタイム。もちろんお手伝いいただけるお時間だけのご参加でも結構です。
次回は10月26日(月)10時から。
※作業しやすい服装でお出かけください。昼食は寺で用意します。
※ご奉仕の可能な時間だけのご参加でも結構です。皆様のご協力をお願い致します。



「輪読会」
現在は『同朋新聞』(真宗大谷派発行)『サンガ』(東本願寺真宗会館 首都圏広報誌)などをご一緒に読み、感想を語り合っています。
「・・・この国では今、加害の記憶を自虐史観として否定する人が多くなってきた。被害とは善であり、加害とは悪でもある。人は自分を善の側に置く。その帰結として悪は説明不能な特異点となり、成敗されることが当然の存在となる。こうして人は人を殺す。自衛や正義の旗のもとに戦争が起きる。だからこそ“殺すな。殺さしめるな(殺させるな)”は重要だ。ブッダが言ったとされるこの有名なフレーズには、よく読むと“殺されるな”がない。被害の側という善ではなく、加害の側という悪からの視点に自分を置いている。ならばここで、真宗門徒なら誰もが、親鸞の“わが心の善くて殺さぬにはあらず、また害せじと思うとも百人千人を殺すこともあるべし”というフレーズを想起するはずだ。善と悪のあいだに境界はない。そもそも自分は善の側になどいない。誰もが悪になりうるのだ。被害者意識が高揚したとき、この悲惨な戦争を回避するために抑止力を高めて、悪い国を
やっつけようという意識に短絡する。そして同じことを繰り返す。すべては自衛のため。どうやら今の国会では、そう考える議員たちが過半数らしい。こんな時代だからこそ、ブッダの教えの真髄を、親鸞の願いを、生きとし生ける多くの人に伝えてほしい」
(『サンガ』ぼくたちのみらい「殺すな殺させるな」より)
森達也さんのこの文章が今回の話し合いのひとつの手がかりとなりました。
学習会というよりも、感じたことを率直に語る会です。次回は10月26日(月)13時から。お気軽にどうぞ。

ワークショップ「キャンドル作りと瞑想の時間」が開催されました。
2015年09月15日
9月11日(金)
ワークショップ「お寺のお堂で、みつろうキャンドルを作って、ともしびを見つめる瞑想の時間」が開催されました。参加者は女性15名プラス住職。
第一部は平井祐子さん(FARADAY代表)の指導による「みつろうキャンドル」作り。みつろう(蜜蝋)とは、ミツバチが巣を作るときに蜂蜜をお腹の蝋分泌腺で蝋に変化させ分泌する透明な蝋。その蝋を触角の長さに六角形に積み上げ、蜂の子供を守るために雨をはじく巣を作る。花粉が付着して色づいていくそうです。
詳細はこちら→http://faradaybellbee.com/



第二部は松田啓子さん(心療カウンセラー)による「ともしびを見つめる瞑想の時間」。心静かに瞑想し真理を観察する「禅定」(大乗仏教の菩薩の修行徳目「六波羅蜜」のひとつ)に通じるものですが、瞑想と言ってもあくまでも体験。本堂の仄かな灯りのなかで、しばらく自作キャンドルのともしびを見つめ、心身がほぐれたところで感想を語り合いました。


終了後の懇親会は、初対面同士が多かったにもかかわらず、さまざまな話題で盛り上がりました。帰り際には「またお寺に遊びに行ってもいいですか?」といううれしい声が・・・。寺や仏教にも少し親しみを感じてもらえたつどいでした。

